『——さぁ、“花は紅、柳は緑!”』
ステリィがタクトを振り下ろすと、その先端からパウダースノーのような光が生まれ、溢れ、言祝ぎのように参加者たちへと降り注いだ。
その神秘的な情景を、参加者も観覧者も歓声を上げて見惚れたが、リラックスタイムは長く続かなかった。
光の粒子は宙を舞い、やがて参加者の花型のバッジへと降りかかった。と、バッジが服から外れ、むくむくと膨れ形を変えていき、フロアにズシンと落ちたのだ。
「きゃぁっ!」
「なに、なになにっ?!」
バッジの成長した姿はそれぞれ異なっていたが、そのどれもが音符型の蕾をつけた植物であることだけ共通していた。
例えば4分音符の蕾をつけたヒマワリ、例えば8分休符のシルエットを描くユリ……
種類も違えば体格も全く異なる植物たちが、根状の足を動かして、参加者たちの前にズシンズシンと近づいてくる。
そんななか……ノクノのバッジが変化したのは赤子ほどしか背のない、16分音符の形をしたスミレだった。
スミレは怯えているのか小さな身体をさらに小さくして、細い葉を震わせている。
どうしていいかわからず、ノクノはそっと声をかけてみた。
「あ、あのー……?」
ぷるぷるぷるぷる、ぷるぷるぷるぷる
しかしスミレの震えは収まらない。
とりあえずノクノはぺこりと小さく会釈をしてみた。
「こんにちは……? はじめまして……?」
ぷる、ぷるぷる、ぷる……
あ、ちょっと震えるの、収まったかな?
ノクノがホッとした瞬間、スミレはクルッと背中を向け、ノクノの前からスタコラと逃げ出した。
「ま、待って~っ!」
慌ててスミレを追って走りだしたノクノだったが、そこでようやく周りの参加者が視界に入り、彼女たちも等しく苦戦していることに気がついた。
とりあえず話しかけてみる少女、花と一緒にハチャメチャなダンスをしている少女。
そのなかでも特別目立っている参加者がいる——ロロワだった。
「ど、どういうこと……?!」
戸惑いの声をあげたロロワの前には、他の少女たちとは比べものにならないほど巨大なデンドロビュームがドーンと聳えていた。
他の少女たちの植物が背丈ほどならロロワの物は優に三倍はあり、ロロワに付いていたせいで力をたっぷり浴びてしまったとしか思えなかった。全音符の形をした白や紫の蕾が、茎ごと身体をくねらせながらロロワを覗き込んでいる。
フェスというよりもストイケイアの植物園と言った方が正しい景観のなか、ステリィの溌剌とした解説が響いている。
『アイドルへの道のりは生半可なものではありません。苦労、苦労、苦労の山! もちろん実力があればトップアイドルになれるというわけではなく、運さえも味方につける必要があります。つまり、なにをきっかけに一世風靡るかわからない!』
ケイオスが『ふむ』とのんびり相づちを打って、
『そのきっかけのひとつとして、このフェスもあるわけだね』
『そこです!』
ステリィはタクトでケイオスをビシッ! と指した。
『歌って踊ってにっこり笑って、それだけがアイドルじゃないでしょう! 例えば、歌えなくても身振りで魅了するアイドル。例えば、踊れなくても博学で知識欲を満たすアイドル、パンチひとつで敵を吹っ飛ばすアイドル。アイドルの形はアイドルの数だけあるッ!』
さすがトップアーティストとして十年以上の長きに渡り大衆の前に立ってきた“星灯りのステリィ”といったところか。
内容はめちゃくちゃなのに、力のこもった叫びを聞いていると、ロロワなど単純なので「そうかも」という気持ちになってくる。
デンドロビュームはくねくねとしている。
ステリィは叫ぶ。
ケイオスは適当なことを言う。
『そのために、今こそブルーム・フェスは形を変えるべきでしょう。そう思いませんかケイオスさん!』
『うんうん、その通り! 停滞と退屈は世界の敵だとも!』
『というわけで、今回はいつもとひと味違います。さぁ、みなさんの個性で、それぞれの蕾を咲かせてくださいね!』
あぁ、とロロワは天を仰いだ。
控え室からアリーナに出て、確かにおかしいとは思ったのだ。
ラディリナとフェスに出ると腹をくくってから、もちろん何の準備もしなかったわけではない。過去のブルーム・フェスの内容について、手に入る限りの情報は集めたつもりだ。
過去のフェスにおいて、ライブ用のステージがアリーナから取り払われ人工芝のフロアになっている、ということはなかった。
アイドルはステージに立つもの、お客さんは座席で歓声を送るもの、なのにどうして取り払ってしまったんだろう……アリーナに出るなり、そう疑問に思った。
ロロワは生まれてからずっとオリヴィと旅をしていたため学校に通ったことはないが、リリカルモナステリオには運動の訓練をするための“体育”というものがあるらしい、ということは知っている。
まるでこれじゃ“体育”みたいだ——素朴に抱いた感想は、当たらずも遠からずだったらしい。
——改めてデンドロビュームを見る。
ステリィの魔法を受けた植物は元気溌剌大はしゃぎ! でロロワの言うことなどちっとも聞いてはくれなさそうだ。
そんななか個性を示せと言われても、付け焼き刃的にアイドルの準備をしたロロワには自信を持ってアピールできるポイントなどなかった。
打つ手無し、と一旦ラディリナの方を窺い見ると、彼女はホウセンカと対峙しているところだった。
ホウセンカは喧嘩っ早いのか、鋸歯状のギザギザがある葉でクイクイと手招いているが、ラディリナはただ歯噛みをすることしかできないようだった。
「……っ!」
これが喧嘩だったら一瞬で片付けてやるのに!
そう言いたげな苛立ちの滲む横顔だ。
歴戦のドラグリッターでもアイドルの闘いは未知のバトルフィールドで、たやすく攻略することはできないようだった。
反対に、実況のステリィは子どもがいい感じの棒を拾ったときのようにタクトくるくると振り回し、心底楽しそうだ。
『——さてさて、皆さん苦戦しているようですねぇ!』
と不意に『そうだ』と何事か思い出したようでタクトを止め、横のケイオスへと水を向けた。
『ケイオスさんは一般参加の予選の方もご覧になったんですよね?』
『あぁ、見させてもらったとも』
ケイオスは大きく頷いて、力強く拳を作る。
『どのデュオも本当に魅力的だったけれど、私が気になったのはエントリーナンバー8番“Scarlet Step”!』
ロロワとラディリナの身体がビクリと跳ねる。
それこそ二人のユニット名だった。
ラディリナは立ちはだかっているホウセンカから視線を外し、大スクリーンに映るケイオスを忌々しそうに見上げた。
「あいつ……言うつもりなんじゃ……」
勝ち気なラディリナだが、今だけはその瞳に焦りが浮かんでいた。彼女が気がかりに思っていることと言えばただひとつだ。
そう、ロロワのこと。
その装いはアイドル志望の少女たちに混じっても違和感のないものだが『別人』に見えるかと問われればやや厳しい。
それでもどうか奇跡が起きて、解説のケイオスに気づかれていませんように……!
しかし二人の祈りは、こうして名指しされたところを見ると儚く散ったらしい。
万事休す。せめて言わないでくれたら……!
ロロワの願いをあざ笑うように解説席のケイオスはますます調子をあげていく。
『“Scarlet Step”は真っ赤な衣装を纏ったラディ少女と、緑色の衣装を纏ったロロワ少女のペアなんだ。見所は卓越した運動能力を持つラディ少女のダンス! もちろんロロワ少女も目がいいのか、それに遅れを取ることはなかったよ』
『おぉ、ケイオスさんがそんなに褒めるなんて、これは期待できそうですね!』
『あぁとも!』
ケイオスは深く頷いたあと、ふと手を目の上にかざし、カメラに抜かれスクリーンに映っているロロワとラディリナをまじまじと見た。
『……ん? 二人とも衣装が予選のときとは違うようだ。さらに華やかなものになっていて、よく似合っているね』
『あの衣装、確かノクノが……』
ステリィは口元に指をやりながらぼそりと独りごち、やがて理解した様子でウンと頷いた。
『——なるほど、確かに素敵な衣装が似合うペアですね!』
『あぁ、特にロロワ少女は中性的なスタイルだから、あのももひきが似合っているね』
ケイオスはウンウンと首を縦に振り、
『お爺ちゃん、あれニーハイって言うんですよ』
ステリィがイヤイヤと首を横に振る。
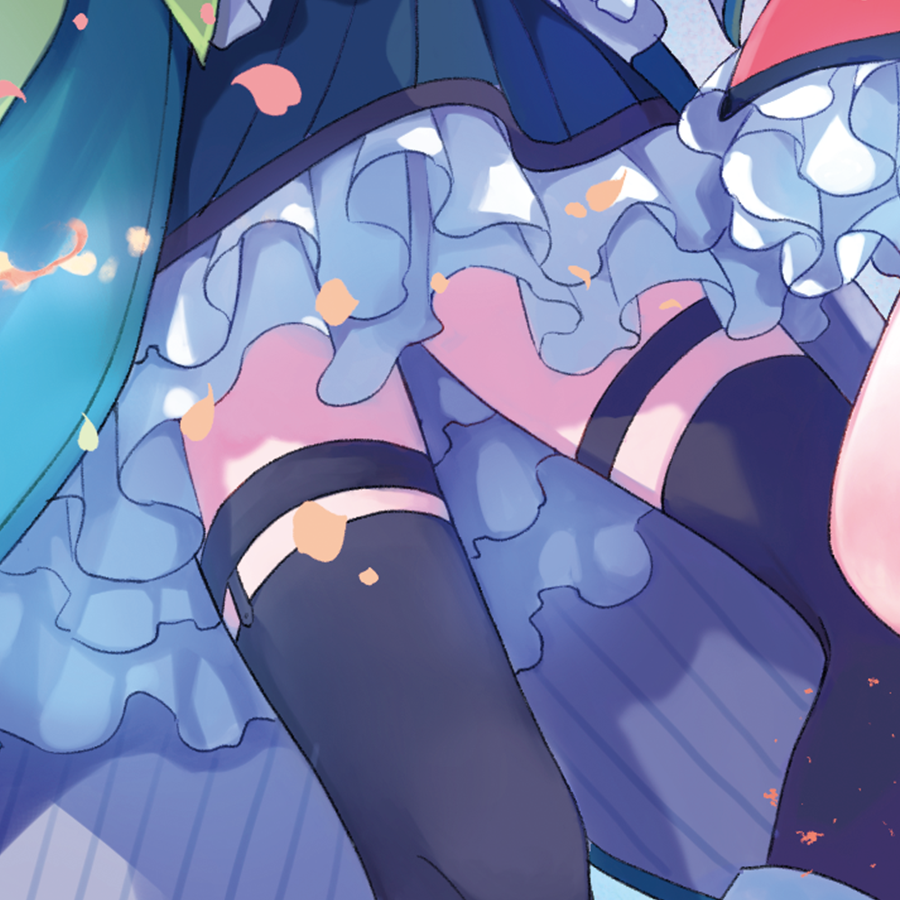
「…………」
ラディリナは深く息を吸い込む。
吐きだす。
殺気で据わった目をしていた。
「ケイオス、亡き者にしましょう」
「ラディ、カメラ、カメラ映ってるから!」
「そう。映らないようにやれば問題ないわね」
「待って!」
しかしラディリナは止まらない。解説者席に向かい、ズシン、ズシン、と重い足音を立てながら歩いていく。
その経路上でラディリナのホウセンカは喧嘩を売るように葉をクイクイとやり続けており——ラディリナは、今戦うべき相手はケイオスではなくこいつである、と思い出したのか侵攻の足取りをやや鈍化させた。
良し!
ロロワはそこに希望を見いだした。
——が。
『あ!』
ケイオスは何事か思い出したように人差し指を立てた。
嫌な予感する。ロロワは希望が急速に消えていくのを感じた。
『ちなみに後ろの従者はソックス派だからラディ少女の衣装の方が好みだと思うな 』
——轟、と紅炎色の狂風が吹く。
道を阻んでいたホウセンカは、ラディリナの激甚な怒気が形をなした強烈な風によって、そのまま真上に吹き飛んだ。
ドラグリッターを騎士たらしめているのは剣技のみにあらず、最後に頼るべきはただ誇り高き魂である。それをはっきりと示す圧倒的な力によって空高く打ち上げられたホウセンカは、そのままなすすべなくフロアに落下した。
ロロワ自身もラディリナの怒気で吹っ飛ばされ、木の葉のように舞い上がりつつ、終わった、と思った。
『おぉっと、なんと彼女の気迫によってホウセンカが吹き飛びました。ここはどこだ、リリカルモナステリオだ、あの少女は何者だ——!』
響き渡るステリィの声。
ラディリナが塵芥を払うように頭を振るうと、髪はめらめらと火がついたようになびき広がった。
戦場で名乗りをあげるように言い放つ。
「——アイドルよ」
『おっと、これはなかなか個性的なアイドルの登場です。どうですかケイオスさん!』
ケイオスは手で大きく○を作った。
『“最高”だそうです!』
見れば、フロアに伸びたホウセンカは蕾を開き、深い緋色の花を咲かせている。
ワァァアァアァァ!
大歓声を巻き起こしつつも、ラディリナは瞳の底に激情を燃やしている。
怒っている、これ以上ないぐらいに。
フロアに転がったままぶるぶるとロロワは震えた。どんな敵と対峙するよりも恐ろしいと思った。
「このフェスでやることが三つあるわ。一つ、最高のアイドルになる。二つ、トロフィをゲットする」
一本、二本、ラディリナはゆっくりと指を立てていく。
三本目——ラディリナは指を揃え、それが剣先であるかのように解説者席のケイオスを指した。
「あいつを生きてここから出さない」
「犯行予告はまずいって!」
高らかな宣言はもちろんカメラに抜かれている。
『——だそうですが、いかがですかケイオスさん』
ステリィに話をふられ、ケイオスはウンウンと嬉しそうに頷いた。
『ふふ、私もアイドルには詳しいんだ。こういうのを“ふぁんさ”と言うのだろう?』
『違うと思いますね!』
……どうやら退場や失格という最悪の事態は免れたらしい。
ロロワが胸を撫で下ろしつつフロアから身を起こすと、すぐ傍にデンドロビュームも吹っ飛ばされ転がっており、パチリと目があった。
「ははは、大変だったね」
「…………」
デンドロビュームは何も言わない。もちろん植物は喋れないためそれは当然のことだが、視線には妙に物言いたげな含みがある。
ロロワは違和感を覚え自分の身なりを見やって——スカートがめくれあがり、ふわふわパニエが露出してしまっていることに気がついた。
「……っ!」
慌ててめくれたスカートを直し、ロロワは耳を熱くさせながら、恐る恐るデンドロビュームの方を窺った。
「み、見えてないですよね……?」
「…………」
デンドロビュームはしばらく動かず沈黙を貫いていたが……やがてポッ、と花を咲かせた。
「なんでっ?!」
『“最高”だそうです!』
ステリィの声が響きわたる。
*
VIPルームのタマユラはガラス窓に鼻先がついてしまうほど大きく身を乗り出し、食い入るようにフェスの様子を見ていた。
体調が悪い時など雁皮紙のように血の気を失うかんばせも、今は澄み切った朝焼け空のように色づいている。
『——大きな拍手を!』
設置されたスピーカーから流れてくるステリィの声に、タマユラはパチパチと無邪気に拍手をした。翡翠のかかった胸はゆっくりと上下している。
「アイドル、というものはこんなに素敵なのですね……!」
まるで影の中に溶け込むように控えていたリリミとララミは、タマユラへそっと声をかけた。
「タマユラさま、そんなに興奮されたら」
「タマユラさま、お身体に触ります」
「いいえ、いいえ。こんなに素敵なものを見ていたら、千年でも万年でも寿命が延びそうですよ」
「……はい」
特殊強化磁器でできた双子の頬は、その丸い曲線に反して硬く冷えきっている。けれど生気に満ちたタマユラのかんばせによって、わずかばかり、けれどはっきりと綻んでいくのだった。
と、穏やかな空気をぶち壊す不届き者がある。
ヴェルストラが自席を立ち、つかつかとタマユラの方に近づいてきたのだ。
「挨拶が遅れて失礼。ヴェルストラだ 」
視線を合わせるために身を屈める仕草は、冗談のように気障ったらしい。
「まぁ、ご丁寧にありがとうございます。タマユラと申します」
「タマユラちゃんはリリカルモナステリオに来るのは初めてか?」
「えぇ。生憎、なかなか遠出ができなかったもので」
かんばせこそ豊かな血色を帯びているものの、着物の袖口から覗く手首は痛々しいほどに華奢で白く、今にも向こうが透けて見えそうだ。
「いいねぇ。なら審査員もいいが、まずは目一杯楽しんでもらわないとな」
「えぇ!」
二人は再び激戦を繰り広げているアリーナへと視線を落とす。
“Scarlet Step”の二人はとても個性的で度肝を抜かれたが、他の参加者たちもまた負けず劣らず魅力的だった。
リリカルモナステリオの一年生だというルーテシアは、同じく一年生の少女チェチェとデュオを組んでの出場だ。ダークステイツ出身のエルフであるルーテシアに対し、チェチェはドラゴンエンパイア出身なのか更紗生地のワンピースを纏ったキョンシーで、二人は少し似通ったアンニュイな雰囲気を漂わせていた。
花と対峙したルーテシアは、最初こそ戸惑った様子だったが、ついに覚悟を決めて手を頭上にかざした。たちまちあたりに神秘的な靄がたちこめ、魔方陣から溢れた光が緞子のように染め上げた。
場を一気に自分の色へと変えたルーテシアに、花も観客も一気に引き込まれたが、それだけでは終わらない。
チェチェは頭の符を翻しながら突き出した両手に靄を纏い、それが衣装の一部であるかのように舞い踊る。
呪術と符術、ドラゴンエンパイアとダークステイツ、対称的な二人がリリカルモナステリオで出会い、ひとつのパフォーマンスを作りあげていた。
ファンタジックなパフォーマンスを魅せている二人から少し離れたところでは、また違ったアプローチで人目を惹いている少女がいる。
ミチュだ 。
彼女のブローチから生まれたのはたくさんの蕾を列状につけたスターチスで、蕾から細い茎にかけてが16分休符の形をしている。
ミチュはスターチスとすぐに意気投合したのか、肩を組み、ハイタッチし、ド派手なダンスを繰り広げていた。
「イッエェ——イッ!」
「——!」
まるで十年来の友達であるかのような息の合いっぷりが微笑ましく、タマユラはウフフと笑みの息を零した。
その隣でヴェルストラは焼けた鉄のような目を眇めている。
「——あれは……」
タマユラは髪を揺らし、ゆっくりと首を傾げた。
「なにか?」
「いや、何でもない! アイドルの嬢ちゃんたちも良いが、それより——」
ヴェルストラは芝居がかった仕草でタマユラの細やかな手を取った。
「ドラゴンエンパイアがこんな至宝を隠していたなんて……オレのサーチ力もまだまだだな。だが、ここで出会えた幸運に感謝したいね」
「あ、あの……? ヴェルストラ様……?」
ヴェルストラはタマユラの手を強く握ったまま離さない。
「困っている顔もまた美しいな。もっと色んな表情が見たくなる……」
さらにタマユラとの距離を詰めようと、ヴェルストラが足に力を込めた——と、そのときだ。
「痛ぁっ!」
ヴェルストラは突然大声をあげ、後ろの首筋を押さえながら飛び跳ねた。
そこに絶対零度よりなお冷たい視線を向けているのは、双子の機械人形だ。
「——害虫がいますね」
感情のない声で言ったのは、タマユラの右脇に控えたリリミである。
「——害虫は速やかに駆除する必要がありますね」
感情のない声で言ったのは、タマユラの左脇に控えたララミである。
二人は大きなヒイラギの葉を握っており、トゲトゲとした葉先はナイフもかくやというほどに鋭い。目にも止まらぬ早さでヴェルストラの首を刺したのだった。
「くっ……」
赤くなった首を押さえつつ、ヴェルストラは憎悪に満ち満ちた視線を受ける。気弱な人間であれば視線だけで失禁してもおかしくないような殺気だが、さすがはブリッツ・インダストリーのヴェルストラ、逃げも隠れもせず睨み返した。
バチバチバチ……!
音さえ聞こえてきそうな剣呑な空気をどう受け取ったのか、タマユラは頬を膨らませて「こらっ」と拳を振り上げた。
「リリミ、ララミ、悪戯をしてはいけません!」
「ごめんなさい」
「ごめんなさい」
リリミとララミは素直に謝ってぺこりと頭を下げる。もちろんヴェルストラにではなくタマユラに、である。
「お利口ですね。そのヒイラギは一体なんですか?」
「魔除けです」
と、リリミ。
「酒狂いの鬼がくれました」
と、ララミ。
「まぁ、あれも心配性ですね。でもトゲトゲして物騒ですから、気をつけて遊ぶんですよ」
「はい、タマユラさま」
と、ララミはコクッと頷く。
ドラゴンエンパイアの東、とある地方でヒイラギは魔除けとしてイワシと一緒に行事ごとのときに飾られることがある。何でも、鬼でさえ逃げていくという。
そのヒイラギをドラゴンエンパイアを出発する折に双子は猩々童子から渡されたのだった。
これは何なのかと問えば、猩々童子は『悪い虫を避けるためだ』と言う。
悪い虫はお前だろう、と双子は思ったが、取るに足りない物でも信心するに越したことはないかと受け取ったのだった。
早速役に立ったところを見ると、やはり蛇の道は蛇、悪い虫は悪い虫をよく知る、という事か。
彼方の猩々童子が盛大なくしゃみをぶっ放しそうなことを双子が考えていると、タマユラはふぅ……と大きな深呼吸をした。
その白い首はしっとりとして、ほつれた金の髪がひと筋張り付いている。
「タマユラさま、お暑いのでは」
「あぁ、そうですね。言われみれば……」
「……っ!」
健康的にはしゃぐタマユラを見ているのが嬉しくて嬉しくて、こんなことを見逃すなんて!
双子は激しい自責の念に打たれ、ビスクの指をギュウッと握りしめた。
VIPルームにそれらしいスイッチが見当たらないところから判ずるに、ドームの空調はどこかで一括で管理しているらしい。
「しばし失礼します」
リリミが小さく一礼してVIPルームから出ていくと、ヴェルストラはタマユラの死角からシッシッと手で払っていた。
しかしリリミがいなくなったとはいえ、ララミはタマユラのそばに控えたままで、一秒たりとも油断することなくヴェルストラに向かい殺気を放っている。
今はそのときではないと判断しただろう。男は一旦引くことにしたようで、軽く鼻に皺を寄せつつ自らの席へと足を向けた。
そして立ち尽くす。
「…………」
ヴェルストラの席には、ヒイラギがぶっ刺さったイワシの頭が突き立っていた。
魔除けである。

